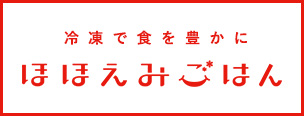広大な更地に未来の工場をつくる。
ニチレイフーズの思いを込めた新工場

更地の状態から完成まで約3年。
次世代を見据えた新工場建設
新工場の建設は、冷凍米飯の需要拡大とBCP(Business Continuity Plan=事業継続)対策、環境負荷低減などを背景に計画が立ち上がりました。ニチレイフーズとして26年ぶり(プロジェクト発足当時)となる国内の新築工場。投資額は約115億円、敷地面積は約20,000㎡、延床面積は約10,200㎡。更地の状態から約3年かけて完成させた、過去最大級の大規模プロジェクトでした。
エンジニアリンググループでは、事業性の検討を皮切りに、建築プランの策定、建物や生産ラインの設計、施工管理、そして稼働までを一気通貫で推進。各分野の専門家や社内の関係者と連携しながら、構想を形にしていく役割を担いました。私自身はキューレイ技術部への出向時にプロジェクトの初期段階から携わり、建物や生産ライン、インフラ設備などのプランニング、工事監理、生産テストを担当。エンジニアリンググループ異動後も生産開始まで携わりました。
新工場では、1.先端技術を活用した省人・省力化、2.おいしさを追求するための新技術開発、3.従業員が働きやすい環境の整備、4.AIを活用した安全安心な取り組み、5.お客様に楽しんでいただけるコンテンツの充実、6.環境負荷軽減を目指した仕組みづくりの「6つのコンセプト」を軸に、ニチレイフーズが考える“次世代の工場”を実現することが求められていました。効率化やコスト最適化だけに注力するのではなく、未来への価値創造を見据えた設備投資を行ったことが、このプロジェクトのポイントだったと感じています。
構想を形にしていく中で最も難しかったのは、検討すべき要素が多く、それぞれが密接に関係していることです。スケジュール、コスト、レイアウト、作業動線、将来的な拡張性。どれも切り離して考えることができないため、エンジニアとして社内外の関係各所と密にコミュニケーションを取りながら最適解を導き出すことが常に問われました。

設計、仕様検討、社内外の調整。
多方面との多岐にわたる検討を重ねる
2021年5月、プロジェクトは本格的な設計フェーズに入りました。この段階から、建物の仕様やレイアウト、設備の配置など、検討すべき項目は一気に膨らみました。
設計フェーズで最も重要だったのは、スケジュールの遅延と予算オーバーをいかに防ぐかという視点です。特に私たちは、関係部署との合意形成を慎重に行いました。一度決まった仕様を後から変更すれば、工程全体が後ろ倒しになり、コスト増にもつながってしまいます。そのため、社内のさまざまな立場の声にしっかりと耳を傾けながらも、優先順位や実現性などを考慮して“落とし所”を見つけ出す必要がありました。
難しさを感じたのは、新たな技術開発と建設設計を同時に進めなければならなかった点です。装置開発の真っ最中に、まだ確定していない仕様を前提に、必要なスペースやインフラ量を見込んで建築条件に反映していくことが求められていました。
さらに生産設備の「量」と「多様性」の面でも苦労しました。原料の荷受けから製品出荷までに関わる設備は180種類以上。必要なインフラの違い、異なる会社で接続を行う配管やダクトの調整、天井高さや排気フード位置の考慮など、細部まで気を配らなければなりませんでした。原料エリア、加工エリア、包装エリアの各設備担当がメーカーから集めた情報を整理し、手戻りが発生しないよう慎重に設計に落とし込んでいきました。
こうした複雑な調整を円滑に進めるために意識していたのは、頭ごなしに否定せずに相手の意見をきちんと聞くこと。たとえ制約が多くても、どうすれば実現できるかを一緒に考え、要望を100%満たすことは叶わなくても、最大限に反映する姿勢を大切にしていました。一方で、建築会社さんや設備メーカーさんなど、専門的な知識や経験をもたれている方と協議をする場合でも相手の提案をそのまま鵜呑みにせず、「本当に最適なのか?」を見極めることもエンジニアの重要な役割でした。

苦悩を乗り越えた先の大きな達成感。
ニチレイフーズのエンジニアとして目指す未来
こうして多くの検討と調整を経て、新工場は2023年4月に稼働を開始しました。構想段階から関わってきた私にとって、試行錯誤を重ねた設備が問題なく動いている様子を目の当たりしたときには、大きな達成感を得られました。
特にうれしかったのは、新設した社員食堂について多くの従業員から喜びや感謝の声を聞けたことです。敷地の別エリアにある既存工場の従業員も新しい食堂を利用するようになったと聞いており、働きやすい環境づくりに貢献できたことは自分の中で非常に大きな意味を持っています。
新工場が掲げる6つのコンセプトは、他拠点の工場にも展開され始めています。今後、国内工場では築年数の増加に伴う老朽化への対応、熟練の従業員の定年退職や人手不足、海外への市場拡大に向けた生産能力強化といった課題に向き合わなければなりません。そうした中で、収益性や効率性を高めつつ、誰もが働きやすい工場をどう作るか。その視点がますます重要になっていくのではないかと考えています。
エンジニアリング機能を外部に委託するのではなく、社員自らが現場の細部まで深く、広く関わる。それがニチレイフーズらしいものづくりの姿勢であり、エンジニアとしてのやりがいでもあります。現場で積み上げた経験を、次のプロジェクト、そして次世代の仲間たちへ。これからも、ニチレイフーズのエンジニアリンググループとしての価値を高めていけるよう努めていきます。

担当者の紹介